


【第5回】実務対応のポイント~書面管理と退職勧奨の注意点~ <連載> 退職と職場環境づくり(全6回)

【第4回】判例から学ぶ②~退職願の撤回はいつまで可能?決定的瞬間を知る~ <連載> 退職と職場環境づくり(全6回)
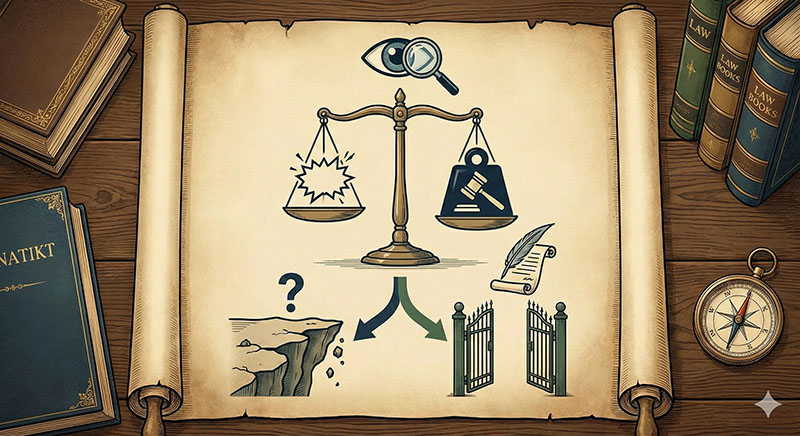
こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!
定年制度シリーズも第3回となりました。今回は、私たち実務家が最も気になる「判例」のお話です。
定年制度は法律の条文だけで形成されてきたわけではありません。個々の労働者と企業の紛争を通じて下された司法判断が、制度の解釈や運用に大きな影響を与えてきました。
特に最近では、定年後再雇用の労働条件をめぐる判断が実務に大きなインパクトを与えています。
面白いことに、定年制度をめぐる司法の争点は時代と共に大きく変化してきました。
初期は制度の「存在」そのもの、特に差別的な適用のあり方が問われました。前回お話しした男女別定年制の無効化などがその典型例です。
ところが、高年齢者雇用安定法によって60歳定年が義務化され、さらに65歳までの雇用確保措置が導入されると、争点は新たな段階へと移行しました。
今度は定年後の「継続雇用(再雇用)」における労働条件、特に賃金の引き下げがどこまで許されるかという問題です。
「定年前と同じ仕事をしているのに、なぜ給料が下がるの?」これは定年後再雇用者からよく聞かれる疑問です。
この問題について、長澤運輸事件や名古屋自動車学校事件などの重要な判例が示されています。
特に注目すべきは、2023年7月の名古屋自動車学校事件の最高裁判決です。
最高裁は、定年前後の基本給の性質や支給目的を具体的に比較検討することなく、単に減額率のみで不合理と判断した二審判決を破棄し、審理を差し戻しました。
これが意味するのは、最高裁が「定年後再雇用には特殊事情がある」という立場を取っていることです。
退職金の支給や老齢厚生年金の受給といった事情を総合的に考慮し、個別の賃金項目ごとに不合理性の有無を判断すべきだ、というメッセージなのです。
これらの判例が企業実務に与える影響は大きいものです。再雇用者の賃金を設定する際に、企業には一定の裁量が認められるものの、その待遇差には合理的な説明が求められるようになりました。
「定年後だから安くて当然」という漠然とした理由では通用しません。職務内容の変化、責任の軽減、年金受給の開始、退職金の支給など、具体的で客観的な理由を整理しておく必要があります。
もう一つの重要な争点が、企業が継続雇用を拒否できる条件です。
高年齢者雇用安定法は希望者全員の継続雇用を原則としていますが、就業規則等で解雇事由や退職事由に該当する場合には、継続雇用しないことが可能です。
ある裁判例では、企業が労使協定で定めた人事考課基準を満たさないとして再雇用を拒否した事案で、裁判所は企業の判断を無効としました。その理由として、「基準は大半の従業員が達成しうる平凡な成績を求めるものと解釈すべき」と判断したのです。
つまり、継続雇用の拒否基準は「普通に働いていれば誰でもクリアできる程度」のものでなければならない、ということです。高いハードルを設定して事実上継続雇用を阻害することは許されないのです。
最近では、定年制そのものを廃止する企業も現れています。
法律上、定年制の設定は義務ではありませんから、廃止することに法的な問題はありません。むしろ、年齢による一律の処遇から、個人の能力や成果に基づく処遇への転換という意味で、時代の要請に合っているとも言えます。
ただし、定年制廃止は労働条件の重大な変更にあたるため、労働者代表との十分な協議が必要です。
また、人事制度全体の見直しも必要となるため、慎重な検討が求められます。
これらの判例が実務に与える示唆は明確です。
第一に、定年後再雇用における労働条件の設定には、より丁寧な検討と説明が必要になりました。
第二に、継続雇用の拒否基準は現実的で達成可能なものでなければなりません。
第三に、定年制度全体の見直しも視野に入れた対応が求められます。
司法判断を追いかけていると、法律が「生きている」ことがよく分かります。
同じ条文でも、時代の変化や社会情勢に応じて解釈が変化し、新たな価値観を反映していくのです。
私たち実務家にとって判例研究は、単なる「お勉強」ではありません。
顧問先企業のリスクを予測し、適切な対応策を提案するための重要なツールなのです。常に最新の判例動向にアンテナを張り、実務への影響を的確に読み取る力を磨いていきましょう。
次回は、定年制度と切っても切れない関係にある「年金制度」について詳しく解説します。
なぜ定年年齢と年金支給開始年齢が連動するのか?将来的な年金制度改革が定年制度に与える影響は?
社会保障制度全体を俯瞰しながらお話ししますので、お楽しみに!