


第2回:「死人テスト」で分かる!従来型就業規則の問題点 <連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)
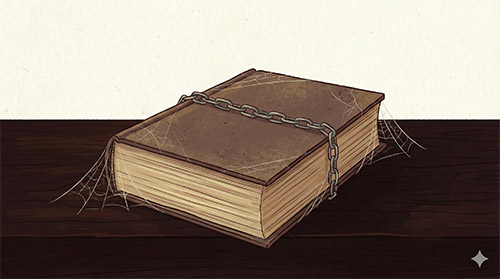
第1回:なぜ就業規則は「読まれない」のか?~形骸化する職場のルールブック~<連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)

こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!
36協定シリーズも今回で最終回となります。これまで基本的な仕組みから実務上の注意点まで解説してきましたが、最後に押さえておきたいのは「36協定を守っていれば大丈夫」という考えが危険であるということです。
今回は、36協定と安全配慮義務の関係、そして働き方の多様化に伴う今後の展望について解説します。
使用者は、労働契約法第5条に基づき、労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負います。
この義務には、過度の労働によって労働者の心身の健康が損なわれないよう注意する義務(健康配慮義務)も含まれます。
この点について画期的な判断を示したのが、過労自殺をめぐる電通事件(最判平12.3.24)です。
この判決は、使用者が36協定の範囲内で労働させていたとしても、それだけで安全配慮義務違反の責任を免れるものではないことを明確にしました。
この判例法理により、使用者には二層構造の義務が課せられることになりました。
1.公法上の義務:労働基準法に基づき、届け出た36協定の条項と時間数上限を遵守し、刑事罰を回避する義務
2.私法上の義務:労働契約法に基づき、36協定の範囲内での労働であっても、個々の労働者の健康状態を具体的に把握し、疲労や心理的負荷の蓄積により心身の健康を損なう危険性が予見できる場合には、業務を軽減するなどの措置を講じる義務
使用者は、「特別条項の範囲内(例えば年720時間以内)なのだから、法的に問題ない」と安易に考えるべきではありません。
36協定が定める上限時間は、あくまで公法上の「最低基準(フロア)」であり、安全配慮義務という観点からは「上限(シーリング)」ではないのです。
安全配慮義務は、個々の労働者の状況に応じて判断される、より柔軟で高度な義務です。例えば、既往症を持つ労働者や、著しい疲労の兆候を見せている労働者に対しては、たとえ月60時間の時間外労働(特別条項の範囲内)であっても、使用者が健康悪化のリスクを予見できたと判断されれば、安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる可能性があります。
働き方改革で特別条項に「健康福祉確保措置」が義務付けられたのは、まさにこの要請を制度化したものと言えます。
特別条項を適用する場合には、医師による面接指導、勤務間インターバルの確保、代償休日の付与といった措置を協定し、実施しなければなりません。
中でも、終業から始業までの間に一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」は、労働時間数だけでなく「休息の質」を確保するものであり、労働者保護の思想的進化を示すものとして注目されます。
労働基準法は、物理的な「事業場」を規制の単位として構築されています。しかし、テレワークやリモートワークの普及は、この「事業場」の概念そのものを曖昧にしています。
労働者の働く場所が自宅である場合、使用者の指揮命令が及ぶ範囲や労働時間の客観的な把握は極めて困難となります。
特に、労働時間と私生活の境界が曖昧になることで、記録に残らない「隠れ残業」が発生しやすく、36協定による時間管理の実効性が損なわれるリスクがあります。
こうした課題に対し、日本経済団体連合会(経団連)などからは、全国一律のテレワーク制度などを円滑に運用するため、規制単位を「事業場」から「企業」へ移行させるべきだとの提言もなされています。これは、労使協定の締結単位をめぐる、今後の大きな法改正の論点となり得ます。
働き方の多様化と個別化が進む中で、今後の労働時間規制のあり方をめぐり、「労使自治」の範囲をどう設定するかが最大の争点となっています。
経団連は、より大きな「労使自治」を志向し、労使の集団的合意によって法律の規定の適用を排除する「デロゲーション」の拡大を提案しています。これに対し、日本労働組合総連合会(連合)は、日本の労使関係には依然として大きな力の差が存在し、安易な「労使自治」の拡大は労働者保護の水準を切り下げる結果につながると主張しています。
この対立は、労働基準法を最低限の「セーフティネット」と捉えるか、不平等な労使関係を是正するための介入と捉えるかという、根本的な思想的対立を反映しています。
労使自治をめぐる思想的対立はあれど、その前提となる「実効性ある労使コミュニケーション」の基盤を強化する必要性については、政労使の間で一定のコンセンサスが形成されつつあります。
過半数代表制度を実効性あるものにするためには、選出プロセスの実質化、代表者の権限・保護の強化、労働者側の意識改革という三つの方向性からのアプローチが不可欠です。
形骸化した労使協定では、真の意味での労働者保護は実現できません。
36協定は、企業の運営に柔軟性をもたらす不可欠なツールであると同時に、重大な法的リスクと社会的責任を伴う制度です。2019年の働き方改革は、その性格を根底から変えました。
もはや、単に様式を整えて届け出るという手続き的コンプライアンスだけでは不十分です。協定の有効性は過半数代表者の適正な選出にかかっており、その運用は協定で定められた手続きの遵守と、それを超える使用者の包括的な安全配慮義務によって厳しく制約されます。
特に、電子申請の普及や押印廃止という現代的な潮流は、36協定の本質である「労使の対話と合意」を希薄化させるリスクを浮き彫りにしました。この形骸化こそが、働き方改革の理念を骨抜きにする最大のアキレス腱です。
36協定は長時間労働の「許可証」ではなく、真にやむを得ない例外を、企業の生産性と労働者の持続可能性を両立させる形で管理するための枠組みとして機能させなければなりません。
その実現に向けた、実効性ある過半数代表制度の構築と、それを通じた労使双方の継続的な努力こそが、新しい時代の労働法制が目指す姿でしょう。
5回にわたって36協定について詳しく解説してきましたが、いかがでしたか?皆さまの実務の参考になれば幸いです。