


第2回:「死人テスト」で分かる!従来型就業規則の問題点 <連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)
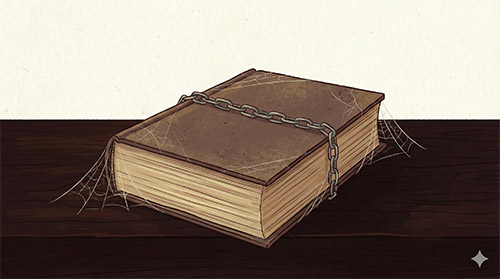
第1回:なぜ就業規則は「読まれない」のか?~形骸化する職場のルールブック~<連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)

こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!
前回はクーリング期間と再休職への対応についてお話ししました。
今回は、円滑な職場復帰を支援するための「リハビリ出勤制度」について、最新の統計データと具体的な運用方法を交えながら詳しく解説していきます。
リハビリ出勤(「試し出勤」「慣らし勤務」などとも呼ばれる)は、長期間の休職やメンタルヘルス不調による休職から復帰する従業員が、スムーズに職場へ再適応するための支援策です。
具体的には、短時間勤務から開始したり、業務負荷を軽減したり、あるいは当初は業務を行わず職場に滞在することから始めたりするなど、個々の回復状況に応じて段階的に進められます。
厚生労働省も、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」や「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」において、このような段階的な復帰や「試し出勤制度」の活用を推奨しています。
労務行政研究所が2024年に実施した調査結果から、リハビリ出勤制度の導入状況について興味深いデータが明らかになっています。
一般疾病の場合、約47%の企業が「認めている」と回答し、精神疾患の場合は約51%の企業が「認めている」と回答しています。
精神疾患の方がわずかに高い割合となっているのは、メンタルヘルス不調からの復帰における段階的なアプローチの重要性が認識されているためと考えられます。
また、大企業ほど導入率が高い傾向があり、通勤交通費を支給する企業が多いことも特徴として挙げられます。
一般疾病で約69%、精神疾患で約71%の企業が「認めている」と回答しており、リハビリ出社よりも導入率が高くなっています。
これは、何らかの業務を行いながら段階的に復帰していくスタイルの方が、企業として導入しやすいことを示しているのかもしれません。
リハビリ勤務を認めている企業における主な内容として、最も多いのは「1日の所定労働時間を調整して勤務」で、90%を超える企業が実施しています。
その他の主な内容としては以下のようなものがあります。
・「時間外労働をさせない」:約83%
・「業務内容の見直し・変更」:約68-74%
・「週の勤務日数を調整して勤務」:約65%
これらの数字は、多くの企業がきめ細やかな配慮をもって復職支援に取り組んでいることを示しています。
労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査では、病気休職制度がある企業の76.8%が「試し出勤制度」を導入していることが明らかになっています。
これは、休職制度を設けている企業の大多数が、復職支援にも積極的に取り組んでいることを示す重要なデータです。
従業員にとって、リハビリ出勤制度には多くのメリットがあります。
まず、本格復帰への不安を軽減できることが挙げられます。長期間の休職後に、いきなり以前と同じ業務量や責任を負うことは、心理的に大きな負担となることが多いのです。
また、徐々に体力や集中力を回復させることができ、復帰前に潜在的な問題点や業務上の困難を把握し、対策を講じることができます。さらに、生活リズムを整え、職場での人間関係を再構築する機会ともなります。
企業にとっても、リハビリ出勤制度には重要なメリットがあります。
最も大きなメリットは、従業員の本格的な復職準備状況を客観的に評価できることです。また、早期の再休職リスクを低減できる効果も期待できます。
厚生労働省のデータによると、企業の98.3%が何らかの休職制度を有し、そのうち66.3%が現にメンタルヘルス不調による休職者を抱えている状況であり、再休職防止は重要な課題となっています。
さらに、従業員への支援姿勢を示すことで、安全配慮義務の履行にも繋がりうるという効果もあります。
また、復帰失敗に伴う採用コストや業務遅延コストの削減も期待できます。
リハビリ出勤には、いくつかの形態があります。
クリニックやリワークセンター、図書館などで勤務時間と同様の時間帯を過ごすものです。職場環境に慣れる前の準備段階として活用されます。
自宅から職場近くまでの通勤経路を辿る訓練です。長期間の休職により、通勤自体が負担となっている場合に有効です。
本来の職場に出勤し、当初は業務を行わずに席で過ごすなどするものです。職場の雰囲気に慣れることを主な目的とします。
短時間勤務や軽微な業務から開始し、徐々に業務量や時間を増やしていくものです。最も一般的な形態といえるでしょう。
リハビリ出勤制度の運用において最も重要なのが、法的地位と賃金の取り扱いです。
試し出勤や通勤訓練のように、会社からの具体的な業務指示がなく、実質的な労働提供がない場合は、一般的に労働とはみなされず、賃金支払義務は発生しません。
この期間、従業員は傷病手当金を受給し続けることが可能です。
ただし、従業員との間で、無給であることについて明確な合意を書面等で得ておくことが極めて重要です。
軽微な作業であっても、会社の指揮命令下で何らかの業務を行う場合は、労働とみなされ、少なくとも最低賃金法に基づく賃金の支払いが必要となります。
NHK名古屋放送局事件(名古屋高判平30.6.26)では、リハビリ出勤中の「テスト出局」が一定の状況下では労働に該当しうると判断されました。
労務行政研究所の2024年調査によると、リハビリ勤務中の賃金について、「不就労時間分は賃金を控除(支給しない)」とする企業が約88%と主流となっています。
これは「ノーワーク・ノーペイの原則」に沿ったものですが、一部でも業務を行わせる場合には、その労働対価としての賃金支払いの要否を慎重に検討する必要があります。
リハビリ出勤が無給で労働とみなされない期間中の事故(例:試し出勤のための通勤途上災害)は、労災保険の対象とならない可能性があります。この点についても事前に従業員に説明し、理解を得ておく必要があります。
リハビリ出勤の期間や内容は、画一的に定めるのではなく、主治医や産業医の意見、本人の回復状況を踏まえて個別具体的に計画する必要があります。進捗状況に応じて柔軟に見直すことも重要です。
主治医および産業医との密な連携は、リハビリ出勤プログラムの策定、実施、評価において不可欠です。医学的な判断なしに企業独自で進めることは、リスクを伴います。
リハビリ出勤制度は、特に精神疾患からの復職支援において、多くの企業で有効な手段として認識され、導入が進んでいます。統計データが示すように、70%を超える企業が何らかの形でリハビリ勤務を導入しており、その重要性は広く認識されています。
ただし、その運用、特に賃金の取り扱いや労災適用の有無については、法的な整理と従業員との明確な合意形成が不可欠です。実質的に業務をさせていながら無給とするような運用は、賃金未払い等の法的紛争を引き起こす原因となります。
次回は、復職判断における重要な考慮事項について詳しく解説します。
原職復帰か代替業務か、主治医と産業医の連携、診断書の取り扱いなど、復職判断の核心となる問題をお伝えしていきます。