


第2回:「死人テスト」で分かる!従来型就業規則の問題点 <連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)
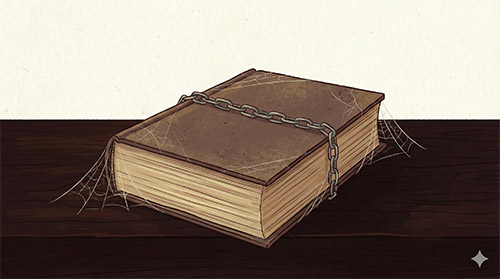
第1回:なぜ就業規則は「読まれない」のか?~形骸化する職場のルールブック~<連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)

こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!
前回は「直接払いの原則」と「使者」「代理人」の区別について解説しました。
今回は第3の原則である「全額払いの原則」について詳しくお伝えします。
この原則には相殺の禁止という重要な論点があり、多くの企業が誤解しやすいポイントでもあります。
全額払いの原則とは、賃金はその全額を労働者に支払わなければならないとする原則です。使用者が一方的に賃金の一部を控除(天引き)したり、支払いを留保したりすることを禁止し、労働者に賃金の全額を確実に受領させることで、労働者の経済生活の安定を保護することが目的です。
この原則は、賃金の一部不払いを背景とした不当な身柄拘束(足止め)を防止する目的も含んでいます。
全額払いの原則の例外として、賃金からの控除が許されるのは次の2つの場合のみです。
第1に、法令に別段の定めがある場合です。所得税の源泉徴収、住民税の特別徴収、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料)などがこれに該当します。これらは法令に基づいて控除が義務付けられているため、労働者の同意や労使協定がなくとも控除できます。
第2に、労使協定がある場合です。当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、またはそのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定を締結した場合には、その協定で定めた項目について控除が認められます。
具体例としては、社宅費・寮費、労働組合費(チェック・オフ)、財形貯蓄の積立金、親睦会費、社員旅行の積立金などがあります。なお、この労使協定は労働基準監督署長への届出は不要です。
全額払いの原則で最も重要なのは、使用者による一方的な相殺の禁止です。これは多くの判例によって確立されたルールです。
関西精機事件(最二小判昭31.11.2)と日本勧業経済会事件(最大判昭36.5.31)では、使用者が労働者に対して有する債権(貸付金返還請求権、損害賠償請求権など)をもって、労働者の賃金債権と一方的に相殺することは禁止されると判示されました。
この禁止は、使用者の債権が労働者の不法行為に基づく損害賠償請求権である場合でも変わりません。賃金が労働者の生活を支える重要な財源であることから、極めて厳格に解釈されています。
しかし、完全に相殺が禁止されているわけではありません。判例上、2つの例外が認められています。
第1の例外:労働者の自由な意思に基づく同意
日新製鋼事件(最二小判平2.11.26)では、使用者が労働者の賃金債権と相殺を行うことについて、労働者がその自由な意思に基づいて同意し、かつその同意が客観的に合理的な理由が存在すると認められる場合には、例外的にその相殺は有効と判示されました。
ただし、「自由な意思に基づく同意」であるか否かの認定は、賃金全額払いの原則の趣旨に鑑み、極めて厳格に行われます。
判断要素としては、同意に至る経緯、相殺の対象となる債権の内容や金額、相殺の条件、労働者の理解度、相殺後の労働者の言動などが総合的に考慮されます。
実務上は、労働者に損害賠償義務が生じた場合でも、使用者が一方的に賃金から天引きすることは許されません。たとえ労働者の同意があったとしても、後日その同意の有効性が争われるリスクがあるため、まずは賃金を全額支払い、その上で別途損害賠償について協議・請求することが望ましいとされています。
第2の例外:調整的相殺
福島県教組事件(最一小判昭44.12.18)では、賃金計算の誤りなどによって賃金が過払いされた場合に、その過払い分を後の賃金支払い時に精算する「調整的相殺」について、厳格な要件のもとで許容されると判示されました。
要件は次のとおりです。時期については、過払いがあった時期と合理的に接着した時期(原則として翌月の賃金支払期)に行われること。方法については、あらかじめ労働者にその旨を予告すること。金額については、控除される額が多額にわたらないこと。そして、労働者の経済生活の安定を著しく害するおそれがないこと。
行政解釈においても、前月分の過払賃金を翌月清算する程度であれば、労基法24条違反とはならないとされています(昭23.9.14基発第1357号)。
実務上よくある問題として、賃金を銀行口座に振り込む際の振込手数料を労働者の賃金から控除するケースがあります。これは、たとえ労働者の同意があったとしても、全額払いの原則に違反し違法と判断される可能性が極めて高いです。
凸版物流ほか1社事件(東京高判平30.2.7)では、即給サービスの利用に伴う振込手数料を労働者の給与から天引きした事案について、労働者の自由な意思に基づく同意とは認められないとして違法と判断し、慰謝料の支払いを命じました。
賃金の支払いは使用者の義務であり、その履行に伴う費用は原則として使用者が負担すべきものです。
社会保険労務士として指導すべきポイントをお伝えします。
労使協定によって賃金から控除を行う場合には、協定が適法に締結されていること、協定内容が明確であること、そして協定内容が労働者に十分に周知されていることを確認しましょう。
使用者が労働者に対して有する債権と賃金との相殺は、原則として禁止されていることを企業に強く認識させる必要があります。安易な「同意に基づく相殺」に頼るのではなく、まずは賃金を全額支払い、その上で別途債権回収を検討するよう助言しましょう。
賃金の過払いが発生した場合の調整的相殺については、福島県教組事件判決が示した要件を厳格に遵守するよう指導します。特に相殺時期は原則翌月、事前の予告、控除額の妥当性、労働者の生活への影響の配慮が重要です。
賃金支払いのための振込手数料は、原則として使用者が負担すべき費用であり、労働者から控除することは違法となる可能性が高いことを明確に伝えましょう。
全額払いの原則は、労働者の生活の安定を保護する極めて重要な原則です。相殺についての判例は、労働者保護の基本理念を堅持しつつも、実務上の必要性を考慮した厳格な要件を示しています。
企業に対しては、例外規定の安易な適用を戒め、賃金の全額支払いを徹底するよう指導することが、社会保険労務士の重要な役割です。
次回は、「毎月1回以上払いの原則」「一定期日払いの原則」、そして「非常時払い」について解説します。これらの原則は、労働者の生活リズムの基盤を形成する重要なルールです。お楽しみに!