


第2回:「死人テスト」で分かる!従来型就業規則の問題点 <連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)
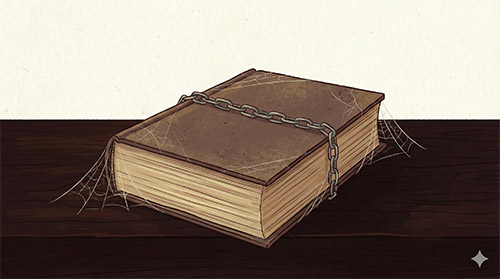
第1回:なぜ就業規則は「読まれない」のか?~形骸化する職場のルールブック~<連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)

こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!
前回は「全額払いの原則」と相殺の禁止について解説しました。
今回は賃金支払5原則の残り2つである「毎月1回以上払いの原則」「一定期日払いの原則」、そして労働基準法第25条の「非常時払い」について詳しくお伝えします。
毎月1回以上払いの原則とは、賃金は少なくとも月に1回以上の頻度で支払われなければならないとする原則です。
ここでいう「1か月」とは、暦の上での毎月1日からその月の末日までを指し、この期間内に少なくとも1回の支払日を設けなければなりません。
この原則の趣旨は、労働者に定期的な収入を確保させ、賃金支払期間が不当に長くなることを防ぎ、労働者の生活の安定を図ることにあります。例えば、2か月分の賃金をまとめて隔月で支払うような方法は認められません。
近年増加している年俸制を採用する場合であっても、この毎月1回以上払いの原則は適用されます。
したがって、年俸額として年間総額が決定されていても、その支払いは毎月1回以上行わなければなりません。
実務上は、年俸額を12分割したり、あるいは賞与分を考慮して14分割や16分割したりして、毎月一定額を支払い、残りを賞与支払時期に支払うといった方法が採られます。ただし、法律上、毎月の支払額を均等にすることまでは求められていません。
年俸で契約した場合でも、その全額を年に1回まとめて支払うことや、半期に一度まとめて支払うことは、この原則に違反します。
この原則には、以下の例外が認められています。
臨時に支払われる賃金として、退職手当、結婚祝金、災害見舞金など、臨時的・突発的事由に基づいて支払われるものや、支給事由の発生が不確定で稀に発生するものが該当します。
賞与についても例外とされていますが、これは定期的または臨時に、原則として労働者の勤務成績等に応じて支給され、その支給額が予め確定していないものに限られます。名称が賞与であっても、支給額や支給時期が確定しているものは、この例外にいう「賞与」には該当しません。
その他、労働基準法施行規則第8条に定める賃金として、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当も例外とされています。
一定期日払いの原則とは、賃金は毎月、一定の期日を定めて支払わなければならないとする原則です。
この原則の趣旨は、労働者が賃金の受取日を正確に予測できるようにし、それに基づいて家賃の支払いやローンの返済など、計画的な生活設計を可能にすることにあります。
「一定の期日」とは、その日付が具体的に特定されている必要があります。適法な例としては、「毎月25日払い」「毎月末日払い」「毎週土曜日払い(週給の場合)」など、日付が固定されるか、または周期的に到来し特定できる定め方です。
違法な例としては、「毎月20日から25日までの間に支払う」のように支払日に幅を持たせる定めや、「毎月第3金曜日」のように暦の関係で月によって支払日が7日程度の範囲で変動する可能性のある定めがあります。
これらは支払日が具体的に特定されているとは言えないためです。
賃金支払日が民法上の休日に当たる場合には、その支払日を繰り上げて支払うことも、繰り下げて支払うことも、就業規則等でその旨を明確に定めておけば認められます。
ただし、月給制で支払日を「毎月末日」と定めている場合に、その末日が休日に当たるからといって翌月の初日に繰り下げて支払うことは、その月の支払いがなくなる(毎月1回以上払いの原則にも抵触する)ため、認められません。この場合は前倒しで支払う必要があります。
労働基準法第25条は、通常の賃金支払原則の例外として、「非常時払い」の制度を設けています。
この規定の趣旨は、労働者またはその収入によって生計を維持する者が、出産、疾病、災害などの非常の事態に遭遇し、急な出費が必要となった場合に、労働者が生活の困難に陥ることを防ぐためです。
通常の支払期日前であっても、既に提供した労働に対する賃金の支払いを請求できる権利を保障するものです。
非常時払いを請求できる要件は、労働基準法第25条及び同法施行規則第9条に具体的に定められています。
請求権者は、労働者本人、またはその労働者の収入によって生計を維持する者です。
「労働者の収入によって生計を維持する者」とは、民法上の扶養義務のある親族に限られず、事実上労働者の収入で生活している者であれば、親族でない同居人なども含まれ得ると解されています。
非常の場合の事由としては、労働者またはその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない事由により1週間以上にわたる帰郷が挙げられています。これらの事由は業務上・業務外を問いません。
請求内容は、上記の非常の場合の費用に充てるために、労働者が請求することです。支払われるべき賃金は、支払期日前であっても、既往の労働(既に労働を提供した分)に対する賃金であり、将来の労働に対する賃金の前払いを請求するものではありません。
社会保険労務士として指導すべきポイントをお伝えします。
年俸制を導入している、または導入を検討している企業に対しては、毎月1回以上の賃金支払義務があることを明確に説明し、適切な分割支払い方法を就業規則や雇用契約書で具体的に定めるよう指導しましょう。
賃金の締切日と支払日の設定が、暦月内に少なくとも1回の支払いが確保されるようになっているか、給与規程や実務運用を確認する必要があります。
支払日が休日に当たる場合の取扱いについて、就業規則等に明確な規定を設け、労働者に周知徹底するよう助言しましょう。特に、後ろ倒しにする場合は、毎月1回以上払いの原則に抵触しないよう注意が必要です。
非常時払いについては、労働者から請求があった場合に備え、あらかじめ社内での対応手順を明確にしておくよう助言します。請求があった際には、まず請求事由が法定の「非常の場合」に該当するかを客観的に確認し、支払うべき賃金があくまで「既往の労働に対する賃金」であることを確認する必要があります。
支払時期については、法律上明確な期限は定められていませんが、非常時払いの趣旨から「遅滞なく」支払う必要があると解されています。
毎月1回以上払いの原則と一定期日払いの原則は、セットで労働者の生活リズムの基盤を形成しています。年俸制のような柔軟な報酬体系においても、これらの原則は労働者の基本的な生活保障として機能します。
非常時払いの規定は、賃金支払いの諸原則が形式的なルール遵守に留まるものではなく、労働者の現実の困難な状況への配慮という実質的な保護思想に根差していることを示す重要な条項です。
企業が新しい報酬制度を導入する際には、これらの基本原則を遵守した設計を行うことが不可欠です。
次回は最終回として、賃金支払原則違反時の罰則と未払い賃金請求、そして実務上の総合的な留意点について解説します。お楽しみに!