


第2回:「死人テスト」で分かる!従来型就業規則の問題点 <連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)
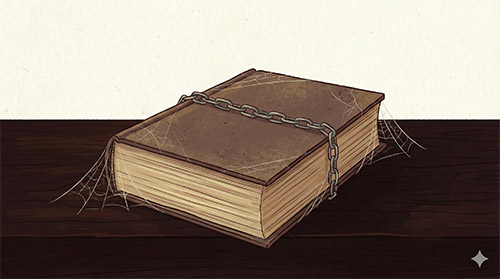
第1回:なぜ就業規則は「読まれない」のか?~形骸化する職場のルールブック~<連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)

こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!
前回は休職命令発令の手続きについて詳しくお話ししました。
今回は、従業員が体調不良により欠勤を始めてから、正式な休職命令に至るまでの移行プロセスについて、実務上の重要なポイントを丁寧に解説していきます。
従業員が体調不良により欠勤する場合、まず年次有給休暇を利用することが一般的です。
これは、休職期間中は原則として無給となる企業が多いため、有給休暇を先に消化する方が従業員にとって経済的に有利となるためです。
ここで重要なのは、企業が従業員に対して有給休暇の取得を強制することはできないという点です。有給休暇の取得はあくまで従業員の権利であり、その申請に基づいて付与されるものです。
従業員が休職を希望しているにもかかわらず、企業側が有給休暇の消化を強要したり、促したりする行為は、法的なリスクを伴います。
実際に、サントリーホールディングスほか事件(東京地方裁判所判決平成26年7月31日)では、企業が休職を申し出た従業員に有給休暇での対応を指示したことが、休職を妨害する不法行為と認定され、損害賠償が命じられました。これは、有給休暇取得の強要が法的に問題視されることを明確に示す重要な判例です。
従業員が有給休暇を取得して休んだ期間が、就業規則に定める休職発令の要件である「欠勤期間」に算入されるか否かは、就業規則の定め方によります。
一般的には、有給休暇を取得した日も「労務の提供がなかった日」として、休職要件たる欠勤期間の算定基礎に含まれると解釈されることが多いようです。
ただし、この点も就業規則で明確にしておくことが、後の紛争を避けるために望ましいでしょう。
多くの企業の就業規則では、私傷病休職の発令要件として「一定期間の連続した欠勤」を定めています。
しかし、うつ病などの精神疾患の場合、必ずしも連続して欠勤するとは限らず、出勤と欠勤を繰り返す(断続的欠勤)ケースが少なくありません。
断続的欠勤の場合、厳格に「連続欠勤」のみを休職要件としていると、実際には就労が困難な状態であるにもかかわらず、休職命令を発令できないという事態が生じ得ます。
これを避けるため、就業規則において、一定期間内の「通算欠勤日数」や「労務提供が不完全な状態」も休職事由として認める規定を設けることが実務上有効です。例えば、「連続または断続を問わず、過去○か月間に通算して○○日以上の欠勤があり、なお療養が必要なとき」といった定め方です。
「連続欠勤」の定義についても、短期間の出勤を挟んだ場合にリセットされるのか、それとも実質的に継続していると見るのか、解釈の余地が生じやすいため、就業規則で可能な限り明確化しておくことが紛争予防に繋がります。
企業によっては、年次有給休暇や本格的な長期の私傷病休職とは別に、比較的短期の傷病による欠勤に対応するための「病気欠勤制度」や「特別傷病休暇制度」を設けている場合があります。
この制度の導入状況について、複数の調査結果から興味深い数値が明らかになっています。
神奈川県産業労働支援センターの調査では、約6割の企業が「病気等休暇・休業制度あり」と回答し、特に大企業ほどその割合が高い傾向にありました。
また、愛知県のデータでは、5割強の企業が「病気休職制度または病気休暇」を導入し、3割弱が「病気事由で使用できる他の制度・方法がある」と回答しています。
これらのデータから、多くの企業が何らかの形で私傷病による欠勤・休職に対応する制度を設けているものの、その内容は多様であることがうかがえます。
正式な長期休職の前に、有給の特別休暇や短期の病気欠勤制度を設けることは、以下のようなメリットがあります。
まず、従業員の安心感を高め、年次有給休暇の計画的な取得を促進する効果が期待できます。従業員が軽度の体調不良で数日間休む場合に、年次有給休暇を全て使い切ってしまうことを避けることができるのです。
また、私傷病休職に至る前のクッションとしての役割を果たし、従業員が無理して出勤したり、将来の大きな病気に備えて有給休暇を温存したりする必要性を減らします。
結果として、職場全体の健康管理や生産性向上に寄与する可能性があります。
病気休暇制度を設計する際には、同一労働同一賃金の観点からの配慮も必要です。
大阪医科薬科大学事件(最判令2.10.13)や日本郵便(東京)事件(最判令2.10.15)では、正社員と非正規社員間での有給の病気休暇制度の待遇差が争点となりました。これらの判決では、正社員に対する手厚い保障は長期雇用を期待し生活保障を図る目的があるといった判断が示されました。
これは、企業が病気休暇制度を設計する際の目的意識の重要性を示唆しています。制度の合理的な根拠を明確にし、適切な制度設計を行うことが求められます。
実務上よくある質問として、「有給休暇を完全に消化しないと欠勤は生じないのか」という点があります。法的にはそのような義務はありません。
従業員は、有給休暇が残っていても、本人の意思で欠勤(無給での休み)を選択したり、就業規則の要件を満たせば私傷病休職を申請したりすることが可能です。
企業が従業員に対し、有給休暇の完全消化を休職の前提条件として強要することは、前述の通り有給休暇取得の強要にあたり、違法となる可能性があります。
私傷病休職に先立つ欠勤期間の管理においては、従業員の権利と企業の円滑な運営のバランスを取ることが重要です。有給休暇の適切な取り扱い、断続的欠勤への対応、そして必要に応じた病気欠勤制度の設計など、きめ細やかな配慮が求められます。
特に重要なのは、就業規則による明確なルール設定です。従業員が安心して療養に専念し、円滑に職場復帰できるような制度設計が、結果として企業の持続的な成長にも繋がる重要な投資と言えるでしょう。
次回は、復職後の再休職への対応として重要な「クーリング期間」と休職期間の通算について詳しく解説します。同一疾病の再発への戦略的な対応方法をお伝えしていきます。