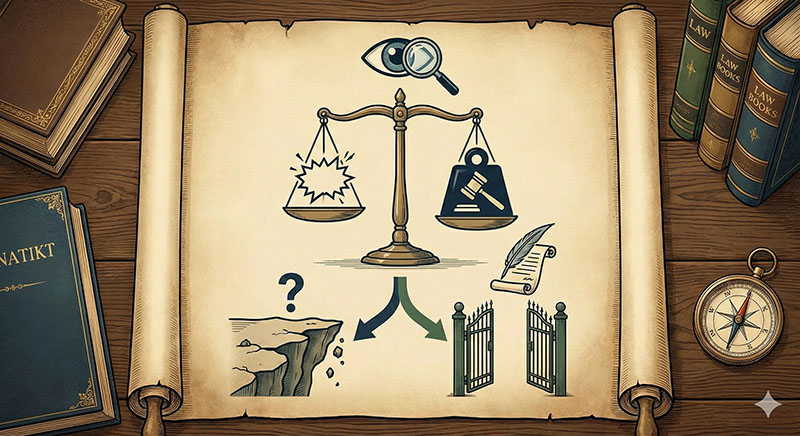
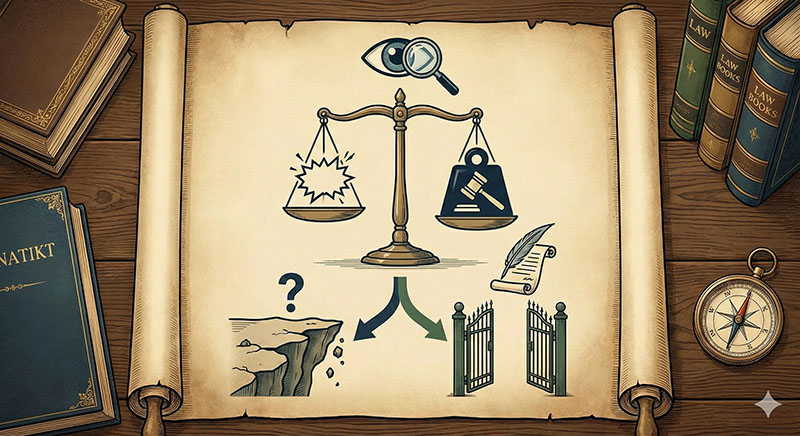
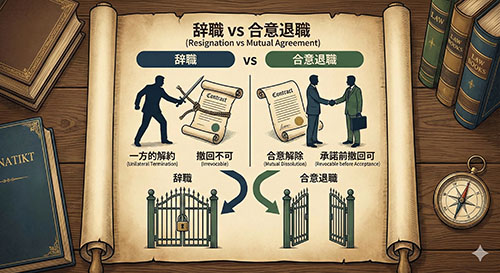
【第2回】「辞職」と「合意退職」の決定的な違い ~知らないと大変なことに!~ <連載> 退職と職場環境づくり(全6回)
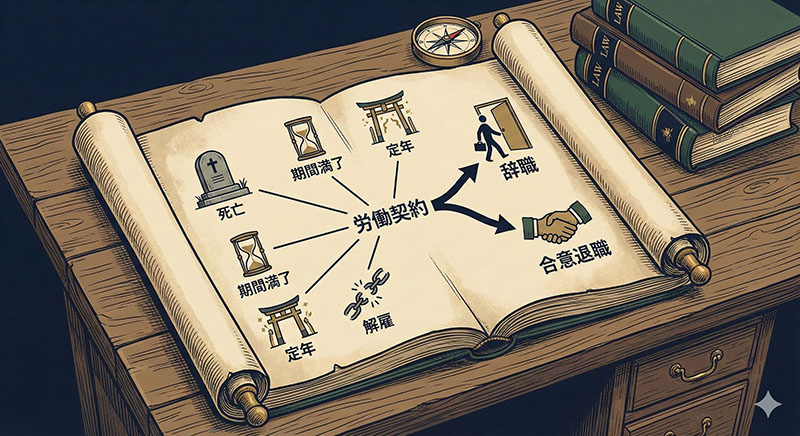
【第1回】なぜ今「退職」の法的理解が重要なのか?~労働契約終了の全体像~ <連載> 退職と職場環境づくり(全6回)

こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!
前回は復職判断の基準と医師との連携についてお話ししました。
今回は、従業員が無事に職場復帰を果たした後の継続的な支援と配慮について、最新の調査データと実務上のポイントを交えながら詳しく解説していきます。
復職後の対応こそが、真の意味での復職支援の成否を決める重要な段階なのです。
復職後の従業員が円滑に業務へ再適応し、安定した就労を継続するためには、個々の状況に応じた労働条件の調整と、それらを具体化した復職プラン(職場復帰支援プラン)の策定・実行が不可欠です。
厚生労働省の各種ガイドラインでは、個別化された職場復帰支援プランの作成が強く推奨されています。
このプランには、以下のような事項を盛り込むことが望ましいとされています。
まず、明確な復職開始日を設定します。次に、必要に応じて変更・軽減された具体的な職務内容を明記します。
労働時間については、多くの場合、当初は短時間勤務(例:半日勤務)から開始し、段階的に通常勤務へ移行する計画を立てます。
就業上の制限としては、残業禁止、特定の業務(例:窓口業務、苦情処理、車両運転など精神的負荷の高い業務や危険作業)の制限、出張制限などを設けることがあります。
フォローアップ体制については、定期的な面談のスケジュール(上司、人事、産業医など)、進捗確認の方法を具体的に決めておきます。さらに、段階的負荷増加の基準として、どのような状態になれば業務量や労働時間を増やしていくかの目安を設定します。
このプランは、従業員本人、直属の上司、人事担当者、産業医が連携し、主治医の意見も参考にしながら作成することが重要です。
復職直後から以前と同様の業務量やフルタイム勤務を求めることは、再発リスクを高めるため避けるべきです。本人の体力や集中力の回復度合いを見ながら、徐々に負荷を上げていくことが基本となります。
職務内容については、一時的に、あるいは必要に応じて恒久的に、本人の状態に合わせた業務内容の変更や負担の軽減を行います。労働時間に関する配慮としては、残業、深夜勤務、交替勤務、出張などの制限は、特に復職初期には一般的な配慮事項です。時差出勤やテレワークといった柔軟な働き方の活用も有効な場合があります。
復職後のフォローアップについて、株式会社Rodinaが2024年12月に実施した調査結果から、興味深い実態が明らかになっています。
この調査によりますと、休職から復職後、十分なフォローを受けたと感じた人はわずか40%に留まっています。これは、多くの復職者が十分な支援を受けていないと感じていることを示す重要なデータです。
不足していたフォロー内容として最も多かったのは「業務量の軽減」で、50%の人が挙げています。これは、復職時に業務負荷の調整が適切に行われていないケースが多いことを示唆しています。
一方で、フォローが十分だと感じた人の62.5%が「上司との定期的な面談」を良い点として挙げており、コミュニケーションの重要性が明確に示されています。
復職者の状態を継続的に把握し、必要なサポートを提供するために、定期的な面談が極めて重要です。
面談は、直属の上司、人事担当者、産業医などが、それぞれの役割に応じて実施します。
復職初期は週に1回程度、その後は月に1回程度など、状況に応じて頻度を調整します。面談では、業務の進捗、体調、職場での人間関係、困っていることなどを丁寧に聴取し、必要に応じて復職プランの見直しや追加的な配慮を検討します。
健康状態と業務遂行能力のモニタリングも重要です。勤怠状況、調整後の業務におけるパフォーマンス、疲労の度合い、集中力、気分の波などを注意深く観察します。従業員本人からの自己申告だけでなく、上司や同僚からの客観的な情報も参考にします(プライバシーへの配慮は必須です)。
復職後の従業員が安定して就労を継続するためには、企業による組織的な再発防止に向けた戦略的な取り組みが不可欠です。
ストレスチェックの結果を本人にフィードバックするだけでなく、集団分析結果を職場環境改善に活かすことが推奨されます。復職者についても、他の従業員と同様にストレスチェックの対象とし、その結果を復職後のフォローアップに活用することが有効です。
気軽に相談できる社内または社外の相談窓口(カウンセラー、産業医、EAPなど)を整備し、従業員に周知徹底します。復職者が再び不調を感じた際に、早期に相談できる体制を整えることが重要です。
従業員自身がストレス対処法を学ぶセルフケア研修や、管理職が部下のメンタルヘルス不調に早期に気づき対応するためのラインケア研修などを実施します。復職者の上司や同僚に対する研修も効果的です。
積極的な復職支援に取り組む企業の事例から、効果的な手法を学ぶことができます。
味の素株式会社では、独自の復職プログラム導入により再発率を一般的な水準の半分に低減させています。また、野村證券では休職者に寄り添った復職支援で再休職率を大幅に削減した事例があります。
これらの企業に共通するのは、復職者個人の状況に応じたきめ細やかな支援と、組織全体での支援体制の構築です。
地域障害者職業センターのリワーク支援や医療機関のデイケアなど、専門的な事業場外資源の活用も再発防止に有効です。企業単独では提供できない専門的なサポートを外部機関と連携して提供することで、より効果的な復職支援が可能となります。
企業は、労働契約法第5条に基づき、従業員がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。この義務は、従業員の復職後も継続します。
企業は、復職した従業員に対し、その健康状態に応じて業務内容や労働時間を調整し、過度な負担がかからないように配慮する義務があります。特に、精神疾患からの復職の場合、再発のリスクを考慮し、慎重な対応が求められます。
復職プランが不適切であったり、プランに沿った配慮がなされなかったり、復職者の不調のサインを見過ごして適切な対応を怠った結果、従業員の病状が悪化または再発した場合、企業は安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる可能性があります。
過去の判例では、長時間労働やハラスメントが原因で健康問題が発生した場合の企業の責任を認めたものや、看護師の有給休暇取得拒否や威圧的叱責(パワハラ)により精神疾患を発症させたとして病院に賠償を命じた事例などがあります。
企業が日頃からハラスメント防止措置を講じ、被害申告に対して適切に対応していたことが評価され、安全配慮義務違反が否定された裁判例もあります。
復職支援においても、策定した復職プランに基づき、誠実にフォローアップを行い、その記録を整備しておくことは、万が一の紛争時に企業の適切な対応を立証する上で重要となります。
復職者が過度なストレスを感じることなく働けるよう、職場環境(物理的環境、業務量、人間関係など)を継続的に評価し、問題があれば改善策を講じることが重要です。
これは、復職者だけでなく、職場全体のメンタルヘルスリテラシーを高め、誰もが働きやすい環境を構築することにも繋がります。
復職後のフォローアップと再発防止策は、単なる努力目標ではなく、企業の法的義務である安全配慮義務の具体的な実践として捉えるべきです。
株式会社Rodinaの調査が示すように、復職後に十分なフォローを受けたと感じる人は40%に留まっており、特に業務量の軽減や上司との定期的な面談といった基本的な配慮が不足している実態があります。
従業員が安心して働き続けられる環境を整備することは、結果として企業の持続的な成長にも繋がる重要な投資と言えるでしょう。個々の復職者に応じたきめ細やかな配慮と、組織全体での支援体制の構築が、成功する復職支援の鍵となります。
次回は最終回として、私傷病休職をめぐる最新判例と実務対応について総括的にお伝えします。
これまでの連載を踏まえ、企業が取るべき戦略的なアプローチについて具体的にお話ししていきます。