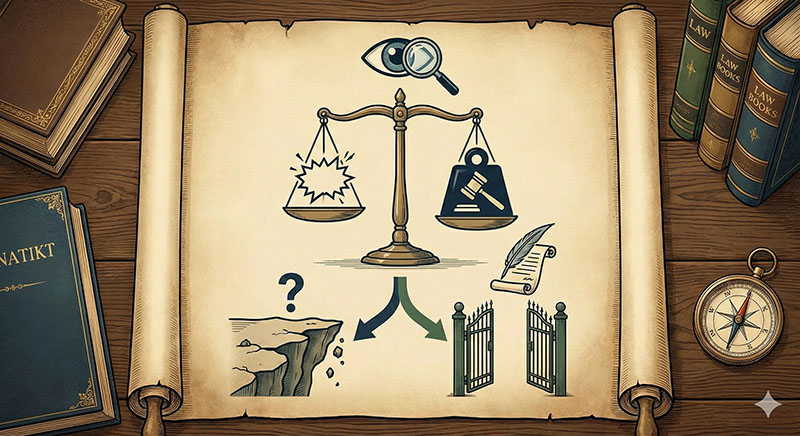
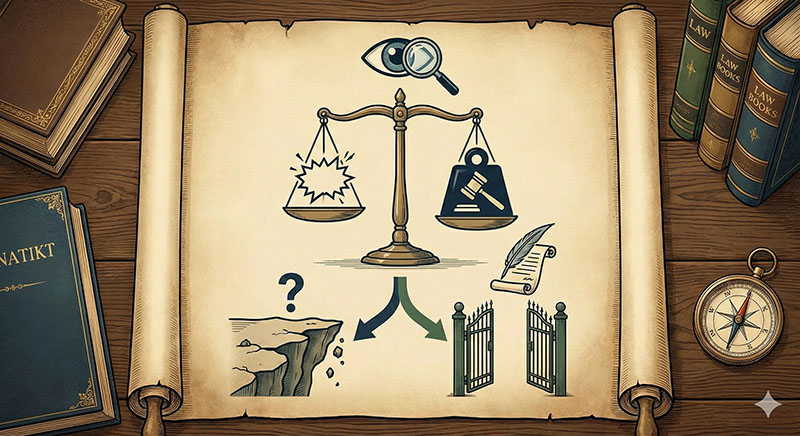
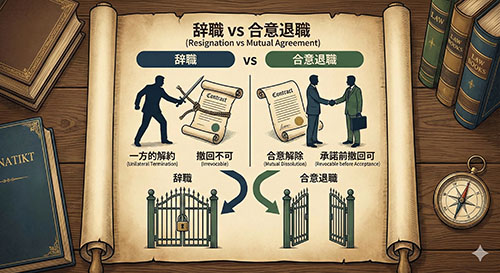
【第2回】「辞職」と「合意退職」の決定的な違い ~知らないと大変なことに!~ <連載> 退職と職場環境づくり(全6回)
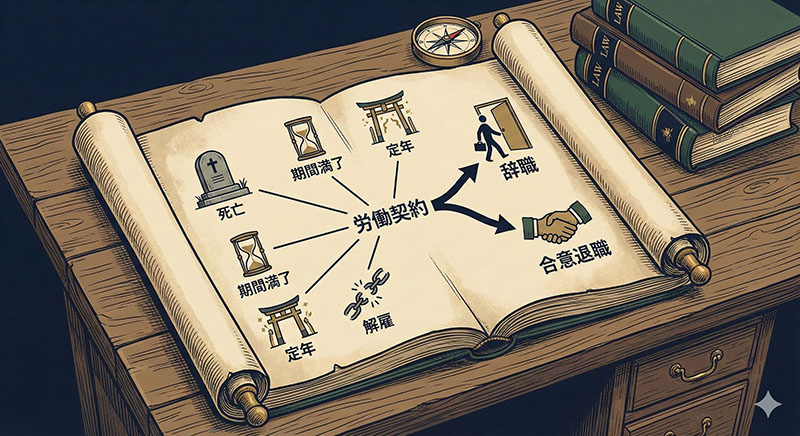
【第1回】なぜ今「退職」の法的理解が重要なのか?~労働契約終了の全体像~ <連載> 退職と職場環境づくり(全6回)

こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!
今回から8回にわたって、日本の労働社会を理解する上で欠かせない「定年制度」について、じっくりと解説していきます。
定年制度は単なる退職の仕組みではありません。
実は、戦後日本の労働慣行、社会保障制度、企業経営、そして個人のライフプランが複雑に絡み合う、まさに「社会経済の変容を映し出す鏡」なのです。
定年制度には、一見すると相反する二つの性格があります。
一つは「定年までの雇用を保障する」という労働者保護の側面。もう一つは「組織の新陳代謝を促し、若年層に機会を提供する」という人材循環の促進機能です。
この二つの機能が絶妙なバランスを保ちながら、日本の雇用システムの根幹を支えてきました。
ところが、少子高齢化という不可逆的な社会変化により、このバランスが崩れ始めています。労働力確保は国家的課題となり、高年齢者の就業延長は社会保障制度の持続可能性を左右する重要な要素となったのです。
「定年制度って戦後にできたものでしょ?」と思われるかもしれませんが、実はその起源は明治時代にまで遡ります。
記録上最古とされるのは、なんと1887年(明治20年)の東京砲兵工廠の職工規定で、55歳を定年と定めていました。民間では1902年(明治35年)の日本郵船が社員休職規則で55歳定年を規定しています。
ここで注目すべきは、当時の日本人の平均寿命が男性43歳前後、女性44歳前後だったことです。つまり、定年年齢は平均寿命を10年以上も上回っていたのです!
文字通り「終身雇用」を体現していたわけですが、実際にその年齢まで働ける人はごく少数でした。
意外なことに、明治時代の定年制は労働者を退出させるためのものではありませんでした。
むしろ逆で、当時は労働市場の流動性が高く、熟練労働者が頻繁に転職していました。企業側は優秀な人材を一定期間確保するための「足止め策」として定年制を導入したのです。現代とは全く異なる発想ですね!
定年制度の性格が根本的に変わったのは第二次世界大戦後のことです。
企業は復員や引き揚げによる過剰な労働力を、整理解雇以外の手段で調整する必要に迫られました。一方、労働者は生活の安定を求め、「定年までは解雇されない」という雇用保障を強く要求するようになりました。
この労使双方の思惑が一致した結果、1950年代から高度経済成長期にかけて、55歳定年制が日本の標準モデルとして定着したのです。
制度の目的が、明治期の「人材確保」から戦後の「雇用調整」と「雇用保障」という二重機能へと大きく転換したわけです。
55歳定年が常識となっていた時代に、次の変革をもたらしたのは年金制度の改正でした。
1954年の厚生年金保険法改正により、男性の年金支給開始年齢が段階的に引き上げられ、1974年には60歳となりました。
これで55歳で定年退職してから年金受給まで「空白の5年間」が生じることになったのです。
この問題を解決するため、労働組合は定年延長を強く要求し、政府も政策的後押しを開始しました。
1986年の高年齢者雇用安定法改正で60歳定年が努力義務となり、1994年の改正で法的義務化、1998年4月から完全施行となったのです。
この歴史を振り返ると、定年制度がいかに時代の要請に応じて変化してきたかがよく分かります。
明治期の人材確保策から、戦後の雇用保障、そして年金制度との調整へ。そして現在は、少子高齢化への対応という新たな課題に直面しています。
定年制度は決して固定的な仕組みではありません。社会経済情勢の変化に応じて柔軟に変化する「生きた制度」なのです。
この視点を持つことで、現在進行中の定年延長や継続雇用制度の意味がより深く理解できるはずです。
次回は、かつて当たり前のように存在していた「男女別定年制」が、どのような過程を経て撤廃されていったかを詳しく解説します。
日産自動車事件という歴史的判決や、職業によって異なる定年制の合理性について、興味深いエピソードを交えながらお話ししますので、お楽しみに!