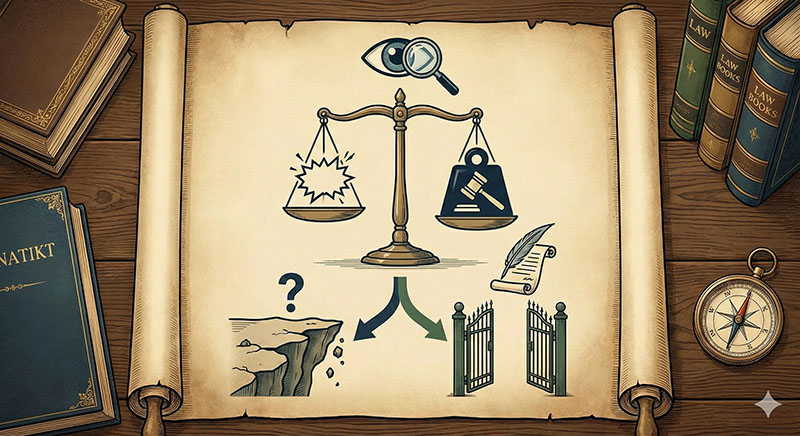
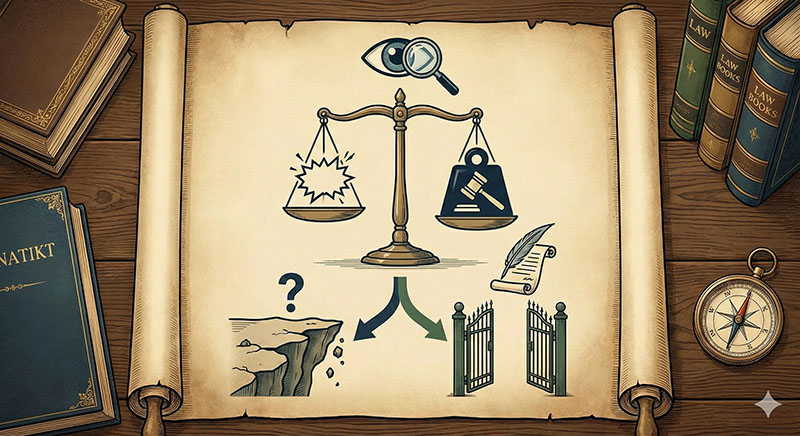
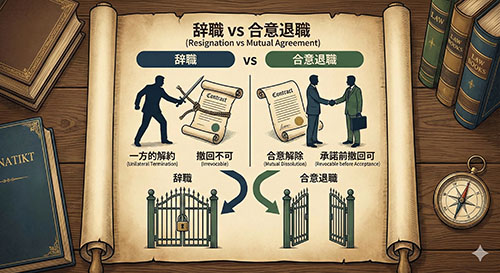
【第2回】「辞職」と「合意退職」の決定的な違い ~知らないと大変なことに!~ <連載> 退職と職場環境づくり(全6回)
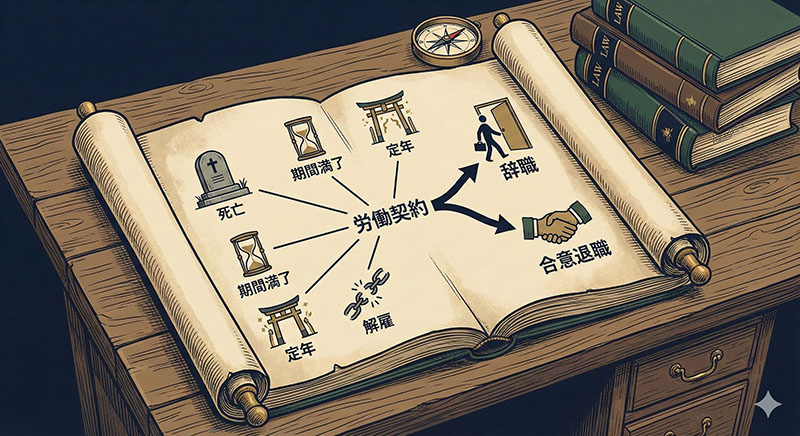
【第1回】なぜ今「退職」の法的理解が重要なのか?~労働契約終了の全体像~ <連載> 退職と職場環境づくり(全6回)

こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!
前回は定年制度の歴史をお話ししましたが、今回は現代の私たちから見ると信じられないような「男女別定年制」の話と、職業によって大きく異なる定年制の興味深い世界をご紹介します。
労働法の歴史において、平等への歩みがどれほど困難で、かつ重要だったかがよく分かる内容です。
今でこそ男女で定年年齢が異なることなど考えられませんが、戦後の日本企業では、男女で異なる定年年齢を設けることが常態化していました。
多くの場合、男性の定年が55歳であるのに対し、女性の定年は50歳や45歳、さらに極端なケースでは30歳という「若年定年制」まで存在していたのです。
さらにひどいのは、女性従業員に対してのみ結婚や出産を機に退職を強いる「結婚退職制」「出産退職制」まであったことです。
これらの制度の背景には、「女性は結婚すれば家庭に入るべき」「高齢の女性は生産性が低い」といった、今思えばとんでもない偏見が根深く存在していました。
この差別的慣行に大きな転換点をもたらしたのが、1981年3月24日の最高裁判所第三小法廷判決、通称「日産自動車事件」です。この事件では、定年を男性55歳、女性50歳と定めていた日産自動車の就業規則の有効性が争われました。
最高裁は明確に判断しました。「性別のみによる不合理な差別」に他ならず、民法第90条の公序良俗に反して無効である、と。
判決では、「女子従業員各個人の能力等の評価を離れて、その全体を上告会社に対する貢献度の上がらない従業員と断定する根拠はない」と述べ、企業側の主張を完全に退けました。
この判決の素晴らしい点は、立法府の動きが鈍い中で、司法が憲法の平等原理を実現するために積極的な役割を果たしたことです。まさに司法が社会変革をリードした画期的な事例でした。
日産自動車事件判決は、1985年の男女雇用機会均等法制定への強力な後押しとなりました。
同法により、募集、採用、配置、昇進から定年・退職・解雇まで、雇用管理の全段階において性別による差別が法律で明確に禁止されることとなったのです。
現在では、性別によって定年年齢に差異を設けることは完全になくなりました。個人の権利を擁護する司法判断が、社会全体の制度改革へと繋がっていく過程は、本当にドラマチックですね。
一方で、すべての職業で定年制が同じというわけではありません。高年齢者雇用安定法が適用される一般の民間企業では60歳以上の定年が義務付けられていますが、職務の特殊性から独自の定年制度を設けている職業があります。
公務員の定年制度は現在大きな変革期にあります。2023年度から定年が従来の60歳から2年に1歳のペースで段階的に引き上げられ、2031年度には65歳に到達する予定です。
ただし、単に定年を延長するだけではありません。60歳以降の給与は原則として7割水準に引き下げられ、管理監督職は「役職定年制」により非管理監督職に降任されます。これは、人件費の抑制と組織の新陳代謝の両立を図る苦心の制度設計と言えるでしょう。
最も特殊なのが自衛官の定年制度です。一般の公務員や民間企業よりも大幅に若い50歳代に設定されています。「えっ、なぜそんなに早いの?」と思われるでしょうが、これにはちゃんとした理由があります。
自衛隊は有事に際して国を防衛するという、極めて高い身体能力を要求される任務を担っています。組織全体の精強さ、つまり隊員の体力・気力を高い水準で維持することが絶対的な要請となるのです。
個人の勤務継続の希望よりも、組織全体の即応性や能力維持という目的が優先されるという、まさに職務の特殊性を体現した制度と言えます。
もちろん、50歳代での退職は隊員の生涯設計に大きな影響を与えるため、「若年定年退職者給付金」制度や再就職支援などの措置が講じられています。
民間企業、公務員、自衛官の各制度を比較すると、定年年齢の「合理性」は一つの基準で測れるものではないことがよく分かります。
社会通念や経済合理性だけでなく、職務の性質、組織の目的、財政的制約といった多様な要素を総合的に判断する必要があるのです。
男女別定年制が当たり前だった時代から、現在の男女平等な制度へ。そして職業によって異なる定年制の存在。
これらすべてが示しているのは、定年制度における「合理性」が時代と文脈によって変化するということです。
私たち社労士は、この「合理性」の変化を敏感に察知し、顧問先企業に適切なアドバイスを提供していく必要があります。制度の背景にある思想や価値観を理解することが、より良い労務管理への第一歩なのです。
次回は、定年制度の解釈と運用に大きな影響を与えてきた重要判例について解説します。
特に、定年後再雇用における労働条件をめぐる最新の司法判断や、継続雇用を拒否できる条件について、実務に直結する内容をお届けしますので、お楽しみに!