


第2回:「死人テスト」で分かる!従来型就業規則の問題点 <連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)
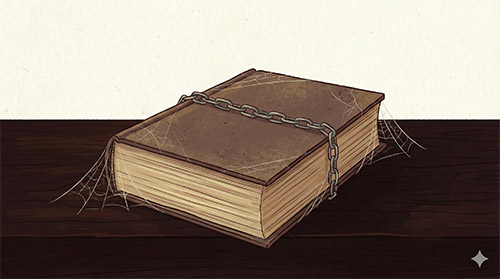
第1回:なぜ就業規則は「読まれない」のか?~形骸化する職場のルールブック~<連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)

今回は変形労働時間制における法定総労働時間枠の重要性についてお話をします。
変形労働時間制は、期間内の労働時間の配分を柔軟にするものですが、期間全体の法定労働時間の総枠(変形期間の暦日数÷7×週法定労働時間)を超えて労働させることを正当化するものではありません。この点を忘れてしまうと、制度の運用に大きな問題が生じる可能性があります。
この点で参考になるのがダイレックス事件(長崎地判令和3年2月26日)です。この事件では、会社が1か月単位の変形労働時間制を採用していましたが、毎月の勤務計画表を作成する際に、所定労働時間に加えてあらかじめ月30時間程度の時間(実質的な固定残業時間)を加算して設定していました。その結果、計画表上の月の総労働時間が法定労働時間の総枠を恒常的に超えていました。
裁判所は、このように法定労働時間の総枠を超えることを前提とした勤務計画は、変形労働時間制の要件を満たさないとして、制度を無効と判断しました。
このケースから明らかなように、変形労働時間制は、あらかじめ見込まれる時間外労働を所定労働時間であるかのように偽装するための手段として利用してはならないのです。あくまで法定労働時間の総枠内で、業務の繁閑に応じて労働時間を弾力的に配分するための制度であることを忘れてはいけません。
法定の総枠を超えて労働させる必要がある場合には、別途、労基法第36条に基づく36協定を締結し、法定の時間外労働として処理し、割増賃金を支払わなければなりません。
当初から法定の総枠を超える労働時間を「所定労働時間」として組み込むような運用は、法の趣旨を逸脱するものであり、許されないことを肝に銘じておきましょう。
■誰よりも顧問先を大切にする社労士の先生はこちらもクリック
↓↓↓
https://academy.3aca.jp/2024a/