


第2回:「死人テスト」で分かる!従来型就業規則の問題点 <連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)
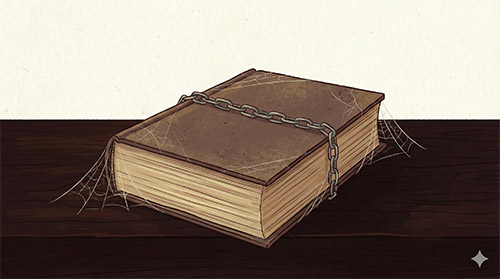
第1回:なぜ就業規則は「読まれない」のか?~形骸化する職場のルールブック~<連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)

今回は変形労働時間制における周知義務の重要性についてお話をします。
変形労働時間制を導入したら、その内容を労働者に適切に周知することが非常に重要です。
就業規則によって制度を導入・規定する場合は、労基法第106条に基づき、常時各作業場の見やすい場所へ掲示したり、書面を交付したりするなどの方法により、労働者に周知させる義務があります。
また、個別の運用においては、特定された各日の労働時間を示す勤務割表等を、変形期間の開始前までに労働者に明示する必要があります。特に1週間単位の変形労働時間制では前週の開始前までに、1年単位で期間を区分する場合には後続期間の開始30日前までに、労働日・労働時間を特定して通知しなければなりません。
裁判例では、周知義務違反そのものが直接的な争点となることは比較的少ないものの、就業規則に勤務割表の作成手続や周知方法が具体的に定められていない場合や、定められた手続きが遵守されていない場合に、労働時間の「特定」が不十分であると判断される一因となることがあります。
例えば、東京地判平成27年12月11日では、就業規則を補完する内部文書が従業員に周知されていなかったことが、変形労働時間制の適用を否定する理由の一つとなりました。
周知は、定められたルール(就業規則、労使協定、勤務割)と、それを適用される労働者とを結びつける橋渡し役を果たします。いかに詳細なルールが文書化されていても、それが労働者に伝わらなければ、労働者は自身の労働時間を予測し、それに備えることができません。
したがって、周知義務の履行は単なる形式的な義務ではなく、変形労働時間制の根幹である労働者の予測可能性を確保するための実質的な要件と捉えるべきです。
企業担当者は、就業規則等で周知の方法(掲示、配布、システムでの通知等)と時期を明確に定め、それを確実に実行することを心がけましょう。
■誰よりも顧問先を大切にする社労士の先生はこちらもクリック
↓↓↓
https://academy.3aca.jp/2024a/