


第2回:「死人テスト」で分かる!従来型就業規則の問題点 <連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)
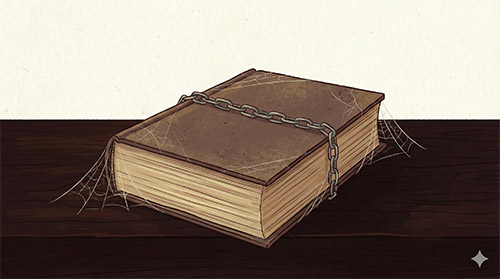
第1回:なぜ就業規則は「読まれない」のか?~形骸化する職場のルールブック~<連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)

今回は変形労働時間制の導入方法と効力について、労使委員会での決議から就業規則の整備までの流れをお話をします。
変形労働時間制は、労使協定の締結だけでなく、労使委員会や労働時間等設定改善委員会の決議によっても導入することが可能です。
平成6年5月31日基発第330号通達では、労基法第38条の4に基づく企画業務型裁量労働制と同様に、労使委員会の5分の4以上の多数による決議や、労働時間等設定改善委員会の決議によっても、変形労働時間制を法的に有効に導入できることが明確化されています。
ただし注意すべき点として、1か月単位と1年単位の変形労働時間制では届出要件に違いがあります。
1か月単位の場合は、労使協定や労使委員会等の決議を労働基準監督署に届け出る法律上の義務はありませんが、1年単位の場合は労基法第32条の4第1項に基づき届出が必要です。
もう一つ重要なのは、変形労働時間制に関する労使協定や委員会の決議そのものは、直接的に労働契約の内容を変更する効果を持たないということです。
これらはあくまで法定労働時間の例外を認めるための「法律要件」であり、個々の労働者の労働契約上の権利義務を直接変動させるものではありません。
そのため、変形労働時間制を有効に機能させるには、就業規則等に「一か月変形(一年変形)の対象者の所定労働時間は、就業規則第〇条の定めに関わらず、一か月変形(一年変形)にかかる労使協定書の定めによるものとする」といった委任条項を設けることが必要です。
この委任条項によって初めて、変形労働時間制に関する労使協定や決議の内容が個別の労働契約の内容として労働者を拘束する効力を持つようになるのです。
また、委任条項を設けた場合でも、労基法89条第1項第2号に従って、就業規則には「始業及び終業の時刻」を記載する必要があります。すべての勤務パターンについて、具体的な始業・終業時刻を就業規則本体またはその別紙等に記載しなければなりません。単に「勤務表による」といった抽象的な記載では足りず、すべての始業・終業時刻のパターンを網羅的に規定することが求められます。
変形労働時間制の導入を検討される際は、これらの手続き面の要件も含めて、慎重に準備を進めることをお勧めします。
■誰よりも顧問先を大切にする社労士の先生はこちらもクリック
↓↓↓
https://academy.3aca.jp/2024a/