


第2回:「死人テスト」で分かる!従来型就業規則の問題点 <連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)
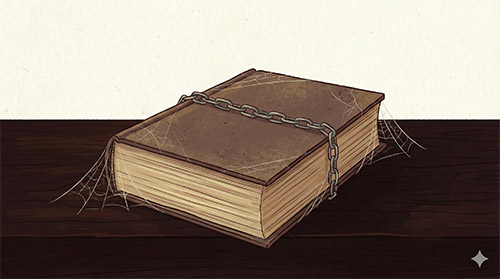
第1回:なぜ就業規則は「読まれない」のか?~形骸化する職場のルールブック~<連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)

今回は勤務ダイヤによる1か月単位の変形労働時間制、特に特殊な業種における運用方法についてお話をします。
鉄道業や交代制勤務を必要とする業種では、業務の特性上、月ごとに勤務表(勤務ダイヤ)を作成して労働時間を管理することが一般的です。
このような勤務形態における1か月単位の変形労働時間制については、昭和63年3月14日基発150号通達(以下「昭和63年通達」)において特別な取扱いが認められています。
昭和63年通達では、業務の実態から月ごとに勤務表を作成する必要がある場合の就業規則の記載要件が明示されています。具体的には「就業規則において各直勤務の始業終業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割の作成手続及びその周知の方法等を定めておき、それに従って各日ごとの勤務割は変形期間の開始前までに具体的に特定することで足りる」としています。
つまり、就業規則本体ですべての勤務パターンを網羅的に記載することが難しい場合でも、①各勤務パターン(直)ごとの始業・終業時刻、②それらの組合せの考え方、③勤務表の作成手続き、④周知方法等を明確に規定し、⑤変形期間開始前に具体的な勤務表を特定・周知することで、変形労働時間制の「特定」要件を満たすことができるのです。
ただし、勤務ダイヤ(勤務表)による変形労働時間制においても、使用者が業務の都合によって労働日や労働時間を任意に変更できるわけではありません。勤務表は必ず変形期間の開始前までに特定し、労働者に周知する必要があります。
また、一度特定された勤務表の変更についても厳格な制限があります。原則として変更はできませんが、例外的に①予見困難な事態発生などの「やむを得ない事由」がある場合であって、②労働者の同意を得るか、あるいは③就業規則に具体的かつ限定的な変更事由と変更手続きが定められている場合に限り、勤務表の変更が認められます。
この昭和63年通達の考え方と日本マクドナルド事件判決は一見矛盾するように思われるかもしれませんが、マクドナルド事件では就業規則にシフトパターンの組合せの考え方や勤務表の作成手続き・周知方法等の定めがなかった点が問題でした。
昭和63年通達が想定するのは、業務の性質上月ごとに勤務表の作成が必要な場合であり、かつ就業規則において勤務パターンの組合せの考え方や作成手続き等が明確に規定されている場合なのです。
変形労働時間制を交代制勤務などの特殊な勤務形態で運用する場合は、この昭和63年通達の要件を満たすよう、就業規則の整備に特に注意を払うことをお勧めします。
■誰よりも顧問先を大切にする社労士の先生はこちらもクリック
↓↓↓
https://academy.3aca.jp/2024a/