


第2回:「死人テスト」で分かる!従来型就業規則の問題点 <連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)
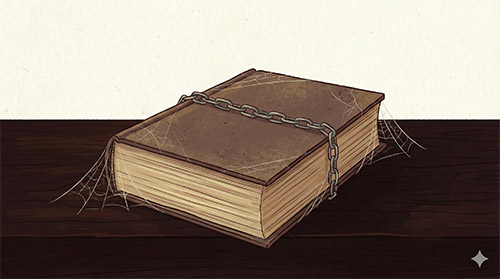
第1回:なぜ就業規則は「読まれない」のか?~形骸化する職場のルールブック~<連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)

こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!
今回から6回にわたって、企業実務でよく見かける「定額残業代」について詳しく解説していきます。この制度、多くの企業で採用されていますが、正しい理解と運用ができていないと思わぬトラブルになることも。まずは基本的な概念から見ていきましょう。
定額残業代(固定残業代、みなし残業代とも呼ばれます)は、実際の残業時間に関わらず、あらかじめ一定時間分の残業代を定額の手当や基本給の一部として支払う制度です。例えば「月30時間分の残業代として8万円を支給します」といった形で設定されるものです。
企業側からすると毎月の給与計算が簡素化できたり人件費の変動を抑えられたりするメリットがあります。従業員側も残業の有無にかかわらず一定の収入が保証される点がメリットとされています。
しかし、この制度は「導入・運用方法を誤ると、労働基準法第37条が定める割増賃金の支払義務を履行したとは認められない」リスクがあります。つまり、きちんと制度設計しないと「残業代のダブルパンチ」と呼ばれる事態に陥る可能性があるのです。
定額残業代の有効性をめぐっては、裁判で争われるケースが後を絶ちません。判例を通じてその有効要件が具体化されてきた経緯があります。不適切な制度設計や運用は、企業にとって予期せぬ多額の支払義務につながる可能性があり、法的な複雑性を理解することが不可欠です。
定額残業代は、一定時間分の時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金として定額で支払われる賃金を指します。これは、実際の労働時間に基づいて計算された割増賃金が、定められた定額の金額に満たない場合でもその定額を支払い、逆に定額を超過した場合には、その差額を追加で支払う義務を伴うものです。
つまり、定額残業代制度は「一定時間までの残業代支払いを免除するもの」ではありません。あくまで割増賃金の支払い方法の一つとして位置づけられています。この点、よく誤解されていますので注意が必要です。
定額残業代が法的に有効と認められるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。これらの要件を満たさない場合、せっかく支払った手当も「通常の労働時間の対価(基本給等)の一部」とみなされてしまい、結果的に全ての時間外労働等に対して割増賃金を別途計算して支払う義務が生じる可能性があります。
次回からは、具体的な有効要件について詳しく解説していきます。「判別性」「対価性」「合意と周知」「差額支払義務」という4つの要件を知ることで、適法な定額残業代制度を設計・運用する土台ができあがります。
定額残業代は、一定時間分の残業代をあらかじめ定額で支払う制度です。企業にとっての事務負担軽減や労働者にとっての収入安定というメリットがある一方、適切に制度設計・運用しないと法的リスクがあります。最も重要なのは、「残業代の支払いを免除する制度ではない」という点です。
次回は、定額残業代が有効と認められるための第一の要件「判別性」について詳しく解説します。お楽しみに!