


第2回:「死人テスト」で分かる!従来型就業規則の問題点 <連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)
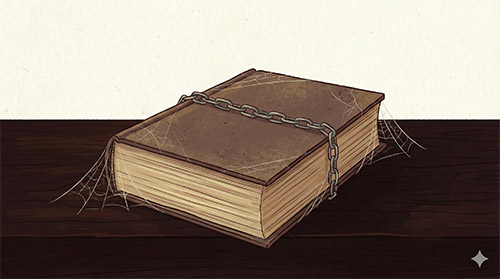
第1回:なぜ就業規則は「読まれない」のか?~形骸化する職場のルールブック~<連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)

こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!
前回は定額残業代の基本的な概念についてお話ししました。今回から4回にわたって、定額残業代が法的に有効と認められるための要件を丁寧に解説していきます。
まずは最も基本的な要件である「判別性」について、皆さまにわかりやすくお伝えします。
「判別性」とは、通常の労働時間の賃金にあたる部分(基本給など)と、時間外労働等に対する割増賃金にあたる部分(定額残業代)とが、はっきりと区別できることを意味します。この要件は、定額残業代制度を適法に運用するための最も基本的な条件なのです。
平成24年3月8日の最高裁判決(テックジャパン事件)では、この「判別性」の重要性が明確に示されました。
この判決によって、基本給と残業代部分がきちんと区分されていない給与体系では、定額残業代が法的に無効となる可能性が高いことが確立されました。
「判別性」が求められる背景には、法的な検証可能性の確保があります。
具体的には、以下の2点を確認するためには、基本給と定額残業代がきちんと区分されていることが前提となります:
1.通常の労働時間の賃金部分が最低賃金を下回っていないか
2.割増賃金部分が労働基準法所定の計算方法(基礎賃金×時間数×割増率)で算定した額を下回っていないか
区分が不明確であれば、基礎となる時間単価を算出できず、割増賃金が適正に支払われているかの検証自体が不可能となってしまいます。
「判別性」を満たすためには、雇用契約書、就業規則(賃金規程)、給与明細書等において、基本給等の通常の賃金部分と定額残業代部分を明確に分けて記載する必要があります。
例えば、こんな記載の仕方では「判別性」が認められません:
・「月給40万円(30時間分の残業代込み)」
これに対して、以下のような記載方法であれば「判別性」の要件を満たします:
・「月給40万円(基本給32万円、固定残業代8万円(30時間分))」
・「基本給32万円、固定残業手当8万円(時間外労働30時間分として支給)」
ここで大切なのは、定額残業代の対象となる時間数だけでなく、その「金額」も明示することです。
厚生労働省も、求人票等において、以下の3点を明示するよう求めています:
1.固定残業代を除いた基本給の額
2.固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
3.固定残業時間を超える労働に対して割増賃金を追加で支払う旨
これらをきちんと明記することで、求職者や従業員が自分の労働条件を正確に理解できるようになります。
テックジャパン事件では、月額41万円の基本給が月間総労働時間140時間から180時間までの労働の対価とされており、その一部が時間外労働に対する割増賃金部分として他の部分と区別されているとは認められませんでした。
このケースでは、月によって勤務日数が変動し総労働時間も変わり得る状況で、41万円の基本給のうち通常の労働時間の賃金部分と時間外割増賃金部分とを判別することは不可能と判断されました。
その結果、会社が41万円を支払っていたとしても、それをもって労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払ったとは認められないという結論に至りました。
「判別性」を欠く場合、支払われた賃金の全額が通常の労働時間の賃金として扱われます。
つまり、定額残業代として支払ったつもりの金額も含めて全額が「基本給」となり、別途計算した時間外労働等の割増賃金を追加で支払う義務が生じるのです。
これが、いわゆる「残業代のダブルパンチ」と呼ばれる事態です。実質的に同じ残業代を二重に支払うことになるため、企業にとって大きな負担となります。
定額残業代制度を適法に運用するための第一歩は「判別性」です。
基本給と定額残業代をきちんと区分し、金額と対象時間を明確にすることで、法的なリスクを回避できます。
「判別性」が確保されているかを確認するためのチェックポイントとしては:
・雇用契約書に基本給と定額残業代の金額がそれぞれ明記されているか
・就業規則や賃金規程に定額残業代の金額と対象時間が具体的に記載されているか
・給与明細書に基本給と定額残業代が区分して表示されているか
次回は、定額残業代の有効要件の2つ目「対価性」について解説します。お楽しみに!