


第2回:「死人テスト」で分かる!従来型就業規則の問題点 <連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)
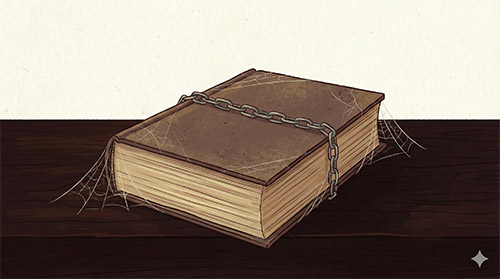
第1回:なぜ就業規則は「読まれない」のか?~形骸化する職場のルールブック~<連載> 服務規定作成のための実践ガイド(全7回)

今回は変形労働時間制を導入する際の「特定」要件の重要性についてお話をします。
変形労働時間制を有効に導入するためには、労働基準法が定める様々な要件を満たす必要がありますが、中でも労働日及び労働時間の「特定」要件は最も重要なポイントの一つです。
労働基準法第32条の2(1か月単位)及び第32条の4(1年単位)では、変形労働時間制を導入する際に、変形期間における「労働日及び労働日ごとの労働時間」をあらかじめ具体的に定めることを要求しています。
これは、労働者が自分がいつ、どのくらいの時間働くことになるのかを事前に予測できるようにし、生活設計を立てられるようにするための重要な要件なのです。
裁判所もこの「特定」要件を非常に重視しており、この要件が満たされていないと判断すれば、変形労働時間制そのものを無効とする判決を出すことが多くなっています。
例えば、日本マクドナルド事件(名古屋地判令和4年10月26日、名古屋高判令和5年6月22日)では、就業規則に代表的な4つのシフトパターンしか記載されておらず、実際に店舗で運用されていた約 200 種類ものシフトパターンが網羅されていなかったために、変形労働時間制が無効とされました。
他にも、岩手第一事件(盛岡地判平成13年2月16日)や、E事件(東京地判令和2年6月25日)など、就業規則に具体的な勤務パターンや作成手続きなどが定められていないケースで変形労働時間制が無効とされた事例が多数あります。
これらの裁判例から分かるように、「特定」要件は単なる形式的な手続きではなく、労働者の生活予測可能性を確保するための実質的な要請なのです。
企業が労働時間を任意に決定できる余地を残すような曖昧な規定や運用は、変形労働時間制の趣旨に反し、無効とされるリスクが高いことに注意しましょう。
■誰よりも顧問先を大切にする社労士の先生はこちらもクリック
↓↓↓
https://academy.3aca.jp/2024a/